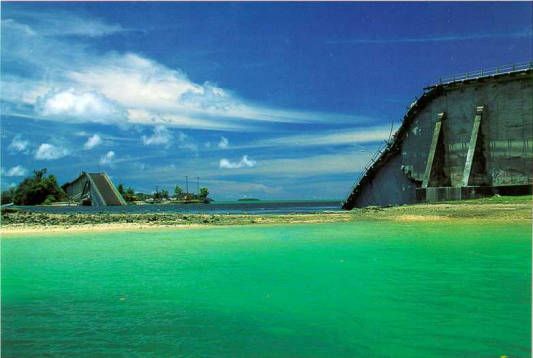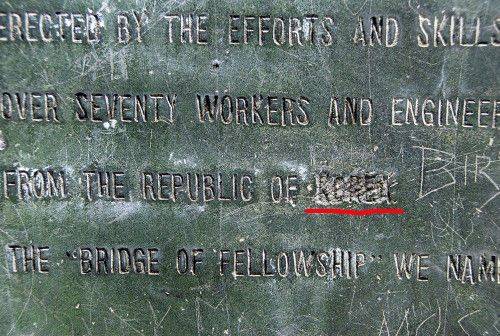転載元
荻上チキ・セッション22 TBSラジオ
2013年6月13日
(大阪市庁舎内 記者会見)
橋下市長
軍自体、日本政府自体が暴行脅迫をして拉致をしたという、女性を拉致をしたという、そういう事実は今のところ証拠として裏付けられていないので、
そこはしっかり言っていかないといけないと思いますよ。
当時、慰安婦制度は各国の軍は持ってたんです。
当時はそういうもんだったんです。
ところが、なぜ欧米の方でね、日本のいわゆる従軍慰安婦問題だけ取り上げられたかと言ったら、
強制的に意に反して、慰安婦を拉致してですね、そういう職業に就かせたと。
レイプ国家だっていうことで、世界は非難してるんだっていうところをね、もっと日本人はね、
世界からどういう目で見られているかっていうところをもっと認識しなきゃいけないです。
------
荻上チキ
最初の論点ですが、橋下市長の発言がありましたが、その件で質問メールが来ています。
『橋下市長の一連の発言について、政治学的、歴史学的な面からどう評価されているか、お聞きしたいです』
秦郁彦
そうですね、まず、その政治的ということはね、歴史観側からはあれこれ言うべきことではないと思いますが、
まぁとにかく舌足らずであったと、そういう部分があちこちに見られたと、その辺が大きくクローズアップされたと思うんですね。
で、これは全然予定してなかったのがちょっと逸れて、この問題に入ったということで、まぁそういうことも考えてあげなきゃいかんだろうと思うんですけども。
事実関係に対してはですね、私は大体その通りだったと、ほぼ正確だったというふうに感じています。
荻上
例えば舌足らずだったというところはどういうところですかね。
秦
例えばですね、新聞報道なんかでは、当時のというのが、最初は抜けてたんですね。
ですから、まさに現在の時点でですね、慰安所は必要であったと、いうふうに彼が考えていると、とられたようですね。
後で言い直しましたよね。
だからこれはですね、聞いてる方もね、彼はずーっと戦後も後の生まれですし、
当時の日本軍の指導者たちが、慰安婦を、慰安所は必要であったと、考えて設立したと。
つまりそういう意味なんですね、本当は。
で、それが意図としてはちょっと舌足らずになっちゃったということでね。
他にもそういうのが何か所かあったと思います。
荻上
そのあとメディアに対して誤報だといったり、論争になったりしたということですけども、
橋下市長の会見について吉見さんはいかが思われたでしょうか。
吉見義明
うーん、まぁ、ちょっとビックリするような、とんでもない発言だったというふうに思いましたね。
というのはですね、舌足らずだったと仰いましたけれども、
慰安婦制度が必要なのは誰だってわかるわけです、というふうに仰っているわけで、これ素直に読めばですね、当時も現在も必要だったという発言になるわけですね。
それとセットになって、事実上、沖縄の米軍に風俗業の活用を勧めると、事実上買春を勧めるという考え方がピタリと平仄が合うわけですよ。
失言だとか舌足らずだとかじゃなくて、本音でそういうふうに言って、未だに撤回していないという点が非常に大きな問題だと思いますね。
荻上
今は許されませんよ、といった発言もそのあとにあったと思いますが、
それは別ということですか。
吉見
在沖米軍に風俗業の活用を勧めるということは撤回されましたけれども、
当時は彼はそれでいいんだというふうに思ってたんでしょうね。
ただし、前の方の発言はマスメディアの誤解だというふうに逃げてるわけですね。
未だに撤回はしてないわけですが、それは非常に不誠実な態度だと思いますね。
(サルメラ 誤解ではない。誤報、あるいは意図的な曲解、慰安婦問題を口にする政治家を問答無用にエジキにしてきたマスコミのいつものやり口だ。
ただ、橋下は他の根性なしの政治家と違い、最後まで謝らなかった、退かなかった、ということだ)
荻上
先ほど秦さんの方が、歴史的な事実に対しては大筋では正しいと言われてましたが、吉見さんは彼の思想とは別に、歴史の認識という面ではどうお考えですか。
吉見
歴史的な事実としても彼はよく知らないということではないかと思いますね。
荻上
どういう点で感じましたか。
吉見
一つは慰安所で女性たちに対する強制があったということ自体を否定しているわけですね。
それから慰安婦制度が性奴隷制度であるということも否定している。
しかし実際に、女性たちは慰安所に閉じ込められてですね、数多くの軍人の性の相手をさせられた。
で、それが非常にひどい状態であるというわけですね。
しかも、慰安所の制度というのは軍がつくった制度ですけれども、例えば居住の自由、もないわけですよ。
それから外出の自由もない。
廃業の自由もない、拒否する自由もない、というような状況のなかで、軍人の性の相手をさせられているわけですので。
そういう事実を彼は見落としてないということでしょう。
荻上
事実をめぐるご意見はお二人それぞれあるので、リスナーの質問を受ける形で、様々議論していただきたいと思います。
南部
次の質問です。
『慰安婦という言葉はいつできて、誰が作った言葉なのか、
そして世界的には慰安婦と同じような意味の言葉はあるのでしょうか。
教えてください』
秦
はっきりしないんですよ。
つまりね、慰安婦というのは少なくとも日中戦争期の軍の公文書のなかにも出てくるんですよね、慰安婦という言葉は。
それに従軍という言葉をつけたのは戦後、千田夏光 氏だといわれてるんですけど。
これもね確実とは言えませんね。
で、慰安婦とですね、どういう存在なのかというと、当時、日本は公娼制、つまり売春をですね、政府が認めてたわけです。
現在でも認めている国がありますけどね。
で、その業に従事している女性たちですね、これを娼妓と呼んでいたわけです。
ですから戦地における娼妓が慰安婦だと、実態はそういうことで、基本的には同じ公娼制のですね、延長線上であったと、考えていいと思います。
荻上
延長線上ということは全く同じものではないということですかね。
秦
まぁ、それはあの、当然のことながら一応戦地ですからね。
だから一番大きな違いはですね、内地の売春婦は、警察が監督してたわけですね。
で、戦地に行った場合には、慰安所の慰安婦たちは憲兵と軍医が監督してたわけです。
その違いですけどね。
憲兵はセキュリティ、つまり秘密漏洩とか、そういうことを防ぐためにですね、やはり関与してたということで、それ以外は大体、形態としてはそのまま延長線上、ということでね、
同じ女性が内地の遊郭で働いていて、今度はその高い給与をね、取れそうだということと、動員が大規模になりますとですね、内地から男はどんどん減っていくんですよ。
戦地に移っちゃうわけですね。
ですから、そこへ移動して同じことをやると、そういう意味です。
荻上
元々、公娼だった方も参加され、その延長線上だったということ、制度としては違う部分はあるけれども、意味合いとしては同じということになるわけですかね。
秦
制度上の違いじゃないですかね。
私に言わせればほぼ同じと考えていい。
荻上
ほぼ同じ。
秦
ええ。
荻上
吉見さんいかがでしょうか。
吉見
両者に関連があるということは言えると思いますけれども、明らかに別のものだと思うんですね。
荻上
公娼と慰安婦制度というものは。
吉見
ええ。
何故かっていうと、内地にある公娼というのは民間の業者が全部運営してるわけです。
軍の慰安所というのはそうではなくて、軍がつくりですね、軍が例えば建物を接収して、業者に使わせる場合もありますけれども、女性を集めるのも、軍が直接やる場合、それから軍が選定した業者に集めさせる場合もありますけれど、軍がやってるわけですよね。
それから慰安所の、規則も料金も軍が決めてるわけですよね、それから実際にそこを利用するのは、軍人、軍属に限られてるわけで、民間人はそこを使えないわけですから、明らかに違う、ということだと思うんですね。
それからもう一つは、内地の公娼制度も、僕は性奴隷制度だと思いますけれども、それはなぜかっていうと、要するに人身売買を基礎にして成り立っているわけですよね。
確かに、人身売買は公認されていて犯罪ではなかったわけですけれども、
慰安婦制度の場合はですね、その公娼制度よりももっと、なんていうんですかね、性奴隷制度の性格が強い。
それは例えば、内地の公娼制度の下ではですね、自由廃業という規定があったわけですね。
これ自由廃業っていうのは娼妓をやめようと思えば、すぐに辞められる権利なんです。
ただこれは実際は、紙の上の権利でしかないわけですけれども、まぁ、一応そういうものがあったわけですが。
荻上
公娼で携わっていた女性の告発とか日記とか見ても、やめさせられないという文章も当時もありましたですし。
吉見
そうですね。
荻上
今もね、風俗などもやめさせてくれない店などあったりしますけれどもね。
吉見
まぁ、建前としては辞められる、自由廃業の規定があったわけですけども、軍の慰安所では自由廃業の規定すらないわけですよ。
それは明らかに違うと思うんです。
荻上
なるほど。
元々の公娼制度も今から考えたら性奴隷的だと取れるし、ましてや軍の関わった慰安所に関しては、公娼よりもさらに進んで酷いという評価は妥当だろうということですかね。
吉見
それからもう一つはですね、国内で人身売買は犯罪ではなかったわけです、当時の刑法で。
国外に連れて行く場合は、国外移送目的人身売買罪というのがきちんとあるわけですよね。
女性たちが人身売買で、海外に連れてかれてですね、慰安所に入れられたとすれば、これは犯罪なわけですよ。
荻上
これは日本政府が犯罪だとしていたと。
吉見
そうですね。
当時の刑法でそれは3年以上の懲役、という非常に重い刑罰を科すことになっていたわけです。
で、仮に、人身売買をされて、慰安所に入れられたとすればですね、慰安所っていうのは軍の施設ですから、
そうすると、そこで女性たちを、いわば使役し続けるわけですから、軍の責任が生じてくる。
犯罪に加担してると言われてもしょうがないということになるわけですね。
それは明らかに違うと思いますね。
荻上
秦さん吉見さんの今の意見どうですかね。
秦
ちょっと私それはね、同意しかねますね。
内地の公娼制をね、これ奴隷だということになってくると、
そうすると、今現在オランダの飾り窓のね、女性たち、ドイツも公認してますしね、それからアメリカでもね、連邦はだめだけれども、ネバダ州は公認してるんですよ。
これみな奴隷、性奴隷てことになりますよね。
吉見
それは人身売買によって女性たちがそこに入れられてるわけですか?
秦
人身売買がなければ、奴隷じゃないわけですか。
志願した人もいるわけでしょ?
高い給料に惹かれてねぇ。
吉見
それは、まぁセックスワークをどういうふうに認めるかということについてはいろいろ議論があってですね。
それはむつかしいわけですけれども、少なくとも、人身売買を基にしてこういうシステムが成り立ってる場合は、
それは性奴隷制というほかないんじゃないですか。
秦
自由志願制の場合どうなるんですか?
吉見
それは性奴隷制とは必ずしも言えないんじゃないでしょうか。
秦
言えない?公娼であっても。
吉見
まぁ、それは本人が自由意思でですね、仮にそういうことを性労働をしているのであれば、それは強制とは言えないし、性奴隷制とも言えないでしょうね。
秦
だからね、日本の身売りっていうのはありましたね。
身売りっていうのはこれは人身売買だから、これいかん、てことになってるんですよ。
日本の法律でね。ですから・・・
吉見
いつ、いかん、てことになってるんですか?
秦
人身売買自体をほら、マリールイズ号事件の時からあるでしょう。ね?
だから、人・・・
吉見
それはだけど、たしかにあるけれども、それは建前なわけですよね。
秦
建前にしろですよ。
それでね、建前にしろですね、人身売買っていうのは、だいたい親が娘を売るわけですけれどもね。
売ったという形にしないわけですよ。
要するに金を借り入れたと。
で、それを返済するまでね、娘が・・・これを年季奉公と言ったりなんかするんですけどね、その間、その性サービスをやらされるってことなんでね。
それでね、娘には必ずしも実情が伝えられてないわけですね。
だからね、しかし、いわゆる身売りなんですね。
あれ昭和・・・
荻上
行ってみたら、こんなはずじゃなかった、というような手記が残っていた場合もあるわけですよね。
秦
騙しと思う場合もあるでしょう。
だから1936年のね、調査っていうのはあるんですが、
こういう売春婦達のですね、調査をやったところ、なぜなったかということについてですね、
家庭の事情というのがね、96%なんですよ。
つまり、娘達は親が自分を売ったということは思いたくないし、
で、そうであってもですね、これは言うに忍びない。
これは朝鮮の場合も同じだと思います。
だからそうするとね、娘たちは、騙されたと感じるのもあるでしょう、親も言いそびれますよね。
だからね、これはね、自由意思か、自由意思でないか、っていうのは非常に難しいんですね。
やはり家族のためにということですと、これ誰が判定するんですか?
吉見
いや、そこに明らかに金を払ってですね、女性の人身を、拘束してるわけですから。
それはもう人身売買というほかないんじゃないですか?
荻上
ちょっと時期は違いますけれども
吉原花魁日記とか、春駒日記とかの大正期の資料なんかには、
親に働いて来いと言われたけど、実際に来てみたら、このことだとは知らなかったと。
このようなケースもあったりするわけですよね。
それは親もあえて騙していたかもしれないし、
周りの人もお金が稼げていいね、と誉のように言うんだけれど、内実の話は周りも知らなかったっていう話は、いろいろあったりしますよね。
吉見
まぁ、実際にはあれでしょ。
売春によって借金を返すっていう、そういうシステムになってるわけでしょ。
秦
今だってそれはあるわけですよ。
吉見
それは、それこそまさに人身売買であって、それが問題になるんじゃないですか?
秦
じゃ、あなた、ネバダ州に行って、あなた、大きな声でそれを弾劾するだけの勇気がありますか?
吉見
いやいや、もし、それがですね、人身売買であればそれはやっぱり弾劾される・・・
秦
いやだから志願してる場合ですよ、自発的に。
自発か、売買か、
どこで区別するんですか。
吉見
いやいや、何を言ってるんですかあなたは!
売春で借金を返済するという、契約の下で・・・
秦
契約じゃないんですよそれは。
回歴後、返済するってことですからね。
大審院はね、逃げても構わないと。
しかし、最後は残ると、いうことですから。
結局やめられないんですよ。親が・・・
吉見
いや、それは、それは当時のですね、判決自体に問題があるわけですよ。
秦
大審院の判決?
吉見
そうです。
秦
だけど、みんな継がなきゃいかんですよ。
当時の人間は・・・
吉見
うん、あの結局ですね、一つの契約を二つに分けてね、売春で借金を返すのは違法だけれども、
借りた借金は返さないといけないっていう、判決がでるから、結局、女性たちは、遊郭から逃れられなかったわけですよ。
荻上
ここでいったん整理させていただきます。
公娼制度の中で、人身売買などの、性奴隷というふうに いわれるケースもあっただろうし、同意のものもあっただろう、
それは個々人によって見てはわからないけれど、
全否定することもできないだろうけれども、
全員がそうだったとも言えないわけですよね。
その実態というのはわからないと。
けれども慰安婦というもののなかで、公娼制度と同じような評価をするのであれば、そうしたものと同程度のものも、それこそ本人の意図に合わないものもあったんじゃないか。
吉見さんの言いたいことっていうのはそういったことなんでしょうかね?
吉見
僕は、日本軍慰安婦制度はですね、一つは人身売買を基礎にして成り立っている。
それからもう一つは、朝鮮から連れてかれた女性たちの中に非常に多いわけですけれども、
騙して連れてかれるケースが多いわけですね。
騙して連れて行くっていうのは当時の刑法でいうと、誘拐罪に該当するわけですよね。
だからその誘拐罪を基礎にして成り立っている。
それからある場合は、法律上でいうと略取と言いますけれども、
暴行脅迫を用いて、連れて行くケースも、あるわけですよね。
それからもう一つ、付け加えて言いますと、例えば占領地なんかでは、軍がですね、地元の有力者に女性を出せというふうに、要求をしますよね。
でこれは、現地の軍がオールマイティなので断れないと。
そうすると誰か犠牲者を差し出せということになるんですが、これは権力濫用による半強制。
中国なんかではこういう例が非常に多かったと思うんですが、
そういうものを基礎にして成り立っているシステムだと思うんですね。
荻上
今の話は意に反して、慰安婦になる人がいたとした場合、その意に反してさせたのはだれか、とつながってくると思うんですけど、秦さんの考えだとどうですかね?
秦
それはねぇ、朝鮮人たちの身の上話であるんですよ。
これがね身の上話AとかBとかね、
酷いのになると一式5通りぐらいあるんですよ。
荻上
証言がですか?
秦
そうそうそう、
それでね、どれが本当かわからないけどね、だからある段階から、朝鮮人の慰安婦のね、慰安婦になった同期としてはですね、主語を全部外しちゃったんですよ。
つまりね、騙されてとか、連行されてと、いうのをね、これ取っちゃったんですね。
荻上
証言の中から?
秦
証言の上からね、で、これはあの、向こうの支援団体の挺対協というのがね、当然、協議してやってると思うんですよ。
荻上
向こうというのは韓国のことですよね。
秦
ええ韓国ですね、ですから、なぜ主語が無いかと言うと、これは私に言わせてもらえば、これ皆、朝鮮人なんですよ。
朝鮮人の親が、朝鮮人のブローカーに売って、そのブローカーが、朝鮮人の抱え主にまた売ると、ね?
いうことで、ここまではほぼ一本ですよ。
この中でね、だから、その中の内情というのはわかりません。
だから一切、それは韓国側からは出てこないわけです。
だから私は初期のころね、ブローカーを見つければね、全貌がすぐわかるよっていうんですけどね、日本はね、そんなことはね、到底、韓国政府には頼めないっちゅうんですよ。
だから一切ブローカーが出てきたことない。
それから親が売ったという話も出てこないわけですね。
だけど大体、私は大多数は今のルートで、それでその抱え主ね、になると、これ日本人もいます。
で、それが戦地に行って、軍と渡りをつけるわけです。
そうすっと、これ需要と供給ですからね、一種の商談なんですよ。
だからどっちが頼んでとか、どっちが主導してとかいう、そういう問題じゃないんですね。
荻上
そうすると、そういう市場があって、それに商品を提供していた側というのはそれこそ韓国の側、ブローカーの側とか、家族の側から提供していたのであって、
そこに騙されたというのがあったとしても、そこに軍の責任などを問われるような類のものではないんじゃないかと、いうことですかね。
秦
それはなぜかって言いますとね、
このブローカーまでの段階というのは、契約というのがあるわけですよね。
それから抱え主との間までも、契約書はある。
それから軍と抱え主との間でね。
連れてきた慰安婦も、それから抱え主も、軍のメンバーじゃないんですよ。
嘱託でもなければ・・・
だから、御用商人なんですよ。
御用商人が女性たちを連れてきていかがですか、と・・・っていうことで商談、一種の商談が行われると。
で、その結果、両方の、需要と供給が合致してですね、それでそこに慰安所ができると。
ま、こういうことですよね。
簡単に言えば。
荻上
一つだけ確認なんですけど、その御用商人というのは、誰でもなれたというわけではないんですか。
ある種の許可制と言いますか、軍の許可証を持ってないと、というのもあるわけですか。
秦
いやいやいや、そうじゃないです。
それはいろいろなコネやなんかでね、ルートをつけて、御用商人って、みんなそうでしょ?
この人は宮中御用達、なんて看板出してるのもありますけれどもね。
あれは一体、本当に認めてるのかどうかわかりませんよね?
納入したこと一回でもあると、そういうふうに言ってるのかもしれません。
だから、私は御用商人だと、考えればいいわけで、
だから民法上の関係はそこで切れちゃうわけです。
だから、軍の方では女性たちがね、どうやって連れてこられたかということはわからない。
荻上
その段階で軍の責任は切れている、という話だと思いますけれど、
吉見さんは今の責任論についてはどうですかね?
吉見
ええとですね、
まず、業者ですけれども、これは軍が選定した業者ですね。
あるいは、軍が頼まれて総督府が選定した業者が集めているわけですよね。
身分は、軍属の待遇を与えられている、と思います。
秦
違います。
吉見
いや違わないですよ。
秦
軍属名簿というのはありますよ、ちゃんと。
それにありません。
だから、軍属待遇っていわれるでしょ?
吉見
ええ。
秦
いかにも軍属と同じだと、ね。
しかし軍属だと給料が払われるはずですよ。
吉見
いや、あの国会のですね、厚生省の答弁なんかでは無給軍属だと、いうような言い方をしてますね。
荻上
無給軍属というのは給料を払われない?
吉見
給料は払われないけれども、純粋の民間人だと軍用船に乗せるわけにもいかないし、軍の施設を使わせるわけにもいかないので、そういう身分を与えているということですね、そういう言い方をすると・・・
秦
女にも与えたということですか?
吉見
そうですね。
秦
女にも軍属の?
吉見
無給軍属。
秦
そんなのはありえませんよ。
吉見
というふうに、厚生省の答弁はしてますよ、ちゃんと・・・
秦
それは一般論の話でしょ?
吉見
一般論じゃなくて、国会答弁でちゃんとそういうふうに・・・
秦
ちゃんと慰安婦もと、言ってるんですか?
吉見
言ってますよ、ちゃんと。
秦
それはありえないですね。
吉見
いや、あの・・・
荻上
それはいつごろの答弁ですか?
吉見
ええっと、ですね。
ちょっと待ってください。
荻上
当時のっていうことですか。
吉見
いや戦後ですね、戦後・・・
秦
南方へ行く場合はね、あらゆる人がね、全部、船に乗っていかにゃいかんわけですよね。
それで船は全部、陸軍がコントロールしてるわけです、配船はね。
だから便宜供与なんですよ、それに乗るいろんな人はね。
吉見
だから民間人は乗れないわけですよね。
秦
いや、乗れますよ、便宜供与で。
吉見
いや、それはだから軍属待遇・・・
秦
たくさん進出してるんですよ、向こうにね。
吉見
軍属待遇にして、いるわけでしょ?
秦
正式な軍属待遇じゃないんですよ。
荻上
特別にこの人たちは船に乗っていいというような形で・・・
秦
ええ。許可するわけですよ。
荻上
その場その場で許可出してるというわけですね。そうなると・・・
吉見
昭和43年の社会労働委員会の会議録、昭和43年4月26日ですね。
『一応、戦地によって、施設宿舎等の便宜を与えるためには何か身分がなればなりませんので、無給の軍属というふうな身分を与えて、宿舎等、便宜を供与していた。
こういう実態でございます。』
という答弁がありますね。
秦
誰ですか、答弁したのは。
吉見
これはですね、サネモト政府委員。
厚生省のお役人だと思うんですが・・・
秦
厚生省がね、それは認識が間違ってますよ。
吉見
いや、実態に合ってるんじゃないですかね。
秦
それはね、軍属待遇にするというね、事例なんか出てないはずですよ。
だからそれはね、乗船許可を出すということはね、「と見なす」というね、
そういうことであってですね、
なんら身分関係はないんですよ。
吉見
それからですね、外務省の公文書によりますと、慰安婦や慰安業者については軍従属者という身分を与えているわけですね。
この軍従属者っていうのは、純粋な民間人ではないということでしょうね。
それからもう一つはですね、その軍によって選定された業者は、例えば人身売買とか、誘拐という犯罪を犯して、女性を海外に連れて行ってですね、軍の慰安所に入れるわけですよね。
で、そのときに、軍の慰安所は女性たちをチェックしないかっていうとチェックしてるわけですよ、くわしく。
秦
どうやってチェックするんですか。
吉見
それは契約関係を調べたりですね、いろんな書類を見てチェックしてるということは・・・
秦
いやー、そいじゃわからんでしょ。
そんなことを書く人はいませんよ。
吉見
いや、それはね・・・
秦
女たちもね、自分はね、無理やりね、連れてこられたなんて言いませんよ。
そしたらね、結局ね、仕事を失うんですよ。
いくらでも補給源はあるわけですからね。
そんなことは言いませんよ。
吉見
いや、そういう例があるんですよ。
言っている・・・
秦
それはインフォーマルにでしょ。
吉見
いやいや、一つの例を示しますとですね、あの有名な、「漢口慰安所」という元軍医さんが書いたあの本の中にですね・・・
秦
あぁ、あの本ですね。
吉見
日本から連れてこられた若い女性がですね、前歴もないと書かれているので、売春の経験のない女性ですね。
その女性が、性病検査の時にですね、
こういう風に言ってるわけですね、私は慰安所というところで、兵隊さんを慰めてあげると聞いてきたのに、こんなところでこんなことをさせられるとは知らなかった。
帰りたい、帰らせてくれ、というふうに泣いて、性病検査を拒んでいる。
その日はできなかった。
翌日、泣き腫らしてですね、体ブルブル震わせながら性病検査に応じるんですが、たぶん業者に殴られてそうされたんだろうというふうに長沢健一さんという軍医さんは言っているわけです。
つまり、慰安所の・・・
荻上
軍の関係者の側が言っているわけですか?
吉見
そうです。
この女性は慰安所で働くということは聞いてるんだけれども、その慰安所というのは何か、軍人の性の相手をさせられるっていうことを知らないできたわけですね。
ですから、これは騙して連れてこられてるわけですから、誘拐罪に該当するはずですね。
秦
だってそれをどうやって立証するんですか。騙したということを。
吉見
いや、この女性がそういうふうに言って・・・
秦
信じるわけですか、その人のいうことを。
吉見
勿論そうですよ。
秦
だってどの程度のね、インテリジェンスのある人かわからないですがね、
慰安所行くといってですね、しかも戦地のですよ、誰かに聞きゃあいいじゃないですか、その辺の大人に。
ね?そうすりゃね・・・
吉見
そりゃあれですよ、秦さんみたいに教養のある人はそうだけれどもですね・・・
秦
だって、そりゃレベルの高い人でしょ?わりと。それ違うんですか。
吉見
いや違いますよ、田舎から連れてこられた女性だというふうに・・・
秦
それを言い出したらね・・・
吉見
いや違いますよ、田舎から連れてこられた女性だというふうに・・・
秦
それを言い出したらね・・・
吉見
それからもう一つ言いますとですね、この女性は重い借金を負っている、というふうに長沢軍医は言っているわけです。
秦
だからそれもおかしいですよね?
吉見
それでつまり、誘拐罪でもありですね、人身売買罪にもなるわけですよ。
ところが、結局この女性は解放されないでそのまま軍の慰安所に入れられてしまうわけですね。
これが犯罪だっていう認識が軍の側にないっていうのは、非常におかしいですよね。
荻上
認識としてということですかね。
吉見
こういう事態が起こったらですね、女性は解放して送り返さなきゃいけないはずですよね。
秦
じゃあその前に業者の方の責任もありますわね。
吉見
業者は逮捕しなきゃいけないということになるわけですね。
そりゃもちろん、送り出した警察もちゃんとチェックしてないという問題もありますよね。
荻上
前提としてそうしたふうに嫌だ嫌だと言った場合は、帰るっていう自由はあったんですか?
秦
借金を返せばね、借金を返せば何の問題もないわけですよ。
吉見
つまり、借金を返すまでに何年間かそこに拘束されるわけですよね。
秦
そうすると親が最後は返さにゃいかんのですよ、親が。
吉見
それが性奴隷制度だっていうことですよ。
秦
親が売ったのが悪いでしょ。
吉見
いやいや、秦さんがわかってないのはそこですよ。
秦
どうして。
吉見
借金を返せば解放される、っていうんであれば、それはあれですよね、人身売買をそのまま認めてることになるじゃないですか。
荻上
ちょっとここで一通、質問メールが来ています。
南部
『従軍慰安婦だった女性たちは戦争が終わった後、無事故郷に帰れたんでしょうか?
多くの人が亡くなったという本を読みましたが、事実はどうだったかを教えてください』
荻上
その本のタイトルも気になりますが、これは秦さん、どうでしょう。
秦
えー、私は自分の本の中でね、それを計算したんです。
生還率は控えめにみて、9割以上と。
荻上
9割以上。
秦
ええ、実際はね、日赤の看護婦さんなんかがね、96%以上なんですよ、生還がね。
大体ね、慰安婦とそれから看護士さんによる野戦病院はね、前線から離れた、比較的安全な場所にいたわけですね。
しかし戦争末期になりますとね、そうもいかなくて、戦闘に巻き込まれたこともあるし逃げ遅れてね、それから玉砕地っていうのがあるでしょ?島でね。
だからそういうのも考慮にしましてね、私は日赤の看護婦さんの、生還率より低かったことはないだろうと。
荻上
そうなると大体9割以上はあるだろうと。
秦
ええ、そうです。
荻上
吉見さん、どれぐらいの方が還られたんでしょうね。
吉見
何%というのを計算したことはないんでわからないんですけれども、たぶん日赤の看護婦さんよりももっと生還率は悪かったんじゃないかと思いますね。
というのは、慰安所の生活というのは非常に厳しくてですね、毎日数人から数十人の男性、軍人の相手をさせられるということが続くわけですよね。
その中で性病を移されたり、体を悪くしたり、そこで病気で亡くなるっていうケースも非常に多いと思いますので、戦地で命を落とした、女性は決して少なくなかったんではないかということは言えると思うんですね。
荻上
まぁ、これももちろん推計ということで、実際にそういった名簿がもちろんあるわけではないので、カウントすることは難しいと思うんですが。
この後も橋下市長の会見などでもしばしば話題になる、強制連行ということもありますし、また軍の関与とか、その後の論争以降の責任の取り方論などの議論のポイントを、続けていきたいと思います。
(サルメラ やや、質問の意図とその回答がズレてるというのが個人的印象。
とくに、吉見教授から聞きたかったのは、
人身売買云々の、誰の責任、誰の罪なのかが まぎらわしい話でなく、もっと直接的な、
『道端歩く女性を突然脅しつけトラックに乗せるという誘拐の例は頻繁にあったのか』
『過労とか病死とかでなく、いわゆる拷問などによるリンチ殺人が特殊でなく、何例もあがっているのか』
というところ、
吉見教授もこうした物語を信じているのか、ということだ)
荻上
強制連行や河野談話の評価についての話をしようと思っているんですが、秦さんから先ほどの議論の補足があるということで、いかがでしょうか。
秦
最近あの、吉見さんがですね、しばしば繰り返して仰ってることなんですけれども、強制連行があったかどうかっていうのは、大した話じゃないと、今はね。
現在は4つの自由がなかった、慰安所における性奴隷というね、こちらの方がずっと重要なんだと、いうことを何度も言っておられるんで。
で、私は強制連行はなかったと思いますけれども、また議論するとね、橋下さんのような議論になっちゃいますんでね。
今の慰安所の状況がそんなに酷いものであったのかどうかと、いうことをちょっと申し上げたいと思うんですけれども・・・
荻上
劣悪な環境で働かされた、だから性奴隷だっていうけれど、そもそも劣悪だったのか疑問があると。
秦
そういうことです。
4つの自由というのはね、これは吉見さんが居住の自由、外出の自由、廃業の自由、接客拒否の自由、がないというね。それをない、
それは慰安所の女性が文字通りの性奴隷だ、というふうに述べておられるわけですよ。
それがところが、吉見さんが編纂された従軍慰安婦資料集というのがあるんですね。
これにですね、1944年、北ビルマに捕えられた韓国人の慰安婦20人に対する米軍の尋問書というのがね、入ってるわけですよ、訳されたものがね。
で、その中でどういう生活だったんだということを聞かれてですね、こういうくだりがあるんです。
『兵隊さんと一緒に、運動会、ピクニック、演芸会、夕食会などに出席して楽しく過ごした。
それから次にですね、お金はたっぷり貰っていたので、暮らし向きは良かった。』
荻上
それは慰安婦当事者の発言ですか?
秦
そうですね、20人の証言です。
それから蓄音機も持ち、都会では買い物に出かけることが許されたと、接客を断る権利も認められたと、それから一部の慰安婦は、朝鮮に帰ることを許されたと。
兵隊さんから結婚申し込みの例はたくさんありましたと、いうのがありましてね。
何よりも月の収入がですね、750円、彼女たちのね、その頃日本の兵隊さんはね、命を的に戦ってるんですけれど、月給は10円ぐらいなんですよ。
つまり、75倍という高収入を得ていたわけですね。
荻上
高収入でなおかつ楽しかったという発言があると。
秦
それもありますね、それから日赤の看護婦さんの10倍です、この金額は。
さらにですね、軍司令官や総理大臣より高いんです、この通りなら。
まぁ、大体似たり寄ったりだったと思うんで。
で、私はこういう状況下にある女性たちがね、性奴隷であったと思えませんね。
雇い主よりも遥かに高い収入を得ている奴隷なんてこの世の中にいます?
荻上
っていうのは、今の吉見さんへの質問ということですね。いかがでしょう。
吉見
ええとですね、まずこれは女性たちがこういうふうに言ったと 仰いましたけれども、
この尋問調書はですね、2名の業者と、それから20人の朝鮮人女性のヒアリングを、アレックス・ヨリチという人が聞いて、まとめてるわけ・・・どの部分が、被害者の女性の証言であり、どの部分が加害者側の証言かよくわからないという点があります。
それからもう一つはですね、将兵と一緒にスポーツ行事に参加したというふうなことがありますが、これは多分ですね、戦地で女性がいないので、慰安婦をそういうところに連れ出すとか、宴会に連れ出すと、いうようなことであったと思います。
夕食会に出席したということも、あると思うんですね。
もう一つは高収入だということですけれども、当時のですね、ビルマのものすごいインフレということをですね、考慮に入れておられないというのは非常におかしなことだと思いますね。
ビルマはですね、軍票を大量に増発して、1943年ごろからものすごいインフレになるわけですね、
荻上
インフレというのはお金の価値が下がるということですよね。
吉見
そうです、1945年になるともう軍票はもうほとんど無価値。
それで女性たちがなぜそれだけのお金を持っているかというと、慰安所に通う軍人がですね、持ってても何も買えないので、チップとして女性たちに渡すわけですよね。
南部
すいません、軍票ってなんでしょう?
吉見
軍隊が占領地で発行する、軍用手票っていう紙幣に代わるものですね。
で、この時期は南洋開発銀行というのがそういうものを出してたわけですよね。
荻上
後ほどお金に引き換えるっていう。
吉見
そうですね、まあ一応。
現地のまあ、例えば1ルピーは日本円で1円ということになっていたんですけれども、内地と比べてですね、ものすごいインフレになるので、外資金庫というのをつくって、そのインフレが内地に及ばないようにしていた訳ですね。
で、現地ではその軍票を持っていても、ほとんど何も買えないので。
荻上
名目上の金額だけだったと。
吉見
ええ、ほとんどそういう状態になってるわけ。
それからもうひとつはですね、秦さんが引用されなかったところがあるんですけれでも、えーと、女性達はですね、それだけのお金を持っているけれども、すぐに生活困難に陥ったと、いうふうなことが書いてあるんですね。
荻上
同じ証言ですか?
吉見
ええ、同じ証言です。
もしそれが高額であればですね、どうして生活困難に陥ることが起こるんでしょうかね?
これはインフレということを考えないとわからないんではないかと思います。
それからもう一つは、同じ引用されたこの「捕虜尋問報告」の一番初めでですね、女性達はどういう形でビルマに連れて来られたのかということを書いてる部分があるんですけれども、その部分を見ますとですね、
こういうふうに言っています。
1942年5月に日本の周旋業者達が朝鮮にやってきて、女性達を集めた訳ですけれども、その役務の、まあ仕事の性格は明示されなかったけれども、それは病院にいる負傷兵を見舞い、包帯を巻いてやり、そして一般的に言えば、将兵を喜ばせる事に関わる仕事であると考えられていた。
これはまあ誘拐ですよね、騙して連れてくるわけですから。
荻上
う~ん。
吉見
それから、これらの周旋業者の用いる誘いの言葉は、多額の金銭と家族の負債を返済する好機、それに楽な仕事と新天地における新生活という将来性である。
これは甘言にあたるので、これも誘拐罪を構成します。
で、このような偽りの説明を信じて多くの女性が海外勤務に応募し、200~300円の前渡し金を受け取った、というふうにありますので、人身売買でもあるわけです。
荻上
う~ん。
吉見
で、こうして、現地で慰安所の生活に拘束されたというふうに書いているんですよね。
荻上
じゃあ、ちょっと今の質問に変えますと、当時インフレだったということを考慮しないのか、というのが一点と、それから、その、今読みあげていただいた方々のそもそも来た理由というものが、甘言、騙されて来ている方々なので、それはどうなんだ、っていう話で・・・
秦
あれは騙したんですよ。
萩上
誰が騙したんでしょうか?
秦
まずほとんど朝鮮人でしょうね。
吉見
これ日本の周旋業者って書いてありますよ。
秦
え?
吉見
日本の周旋業者が朝鮮にやってきて・・・
秦
日本人のですか?
吉見
いやいや、日本のだから日本人でしょう。
秦
いや、当時、日本人なんですよ朝鮮人はね。いや、だいたいね・・・
吉見
それはですね・・・
秦
当時ね、朝鮮に住んでた日本人でね、朝鮮語でね、朝鮮人を騙せるほどね、朝鮮語の上手い人、ほとんどひとりもいなかったと思います。
だから、騙せませんよ。
吉見
元締めが、日本の業者で、手足としてですね、地元の業者を使うということはよくあることですよね。
それから、この周旋業者というのは軍に選定された人物であって、軍から色々、便宜を計ってもらって、まあ誘拐とか人身売買やってるわけですよね。
しかしこれは犯罪なわけでしょ。
それで、連れてった元はどこに入れるかっていうと、軍の施設である慰安所に入れるわけですよね。
そうするとそこで軍の責任は発生しないんですか?
どういうふうにお考えですか?
秦
そこは関係がないわけですよ。
朝鮮総督府の管内で、ですよ。
吉見
いやいや・・・
秦
朝鮮人が、騙したということね。
で、それをね、ちゃんとその旅行許可を出してるわけでしょ。
そうするとね、朝鮮人の巡査もいたわけですな。
それでどうしてそういう騙しを摘発しなかったんですか?
萩上
う~ん。
あのちょっと先ほどの話に戻ってですね、気になったのが、先ほど、そういった証言もあって楽しかったという話もあったということなんですけれども、それは他の慰安所でも同様に楽しかったということになるんでしょうか?
秦
例えばね、こういうのがあります。
文玉珠(ムン・オクチュ)というね、慰安婦なんですがね。
彼女の一代記が本になってるんですよ。
これがね、山川菊枝賞をもらったと・・・
荻上
当事者の発言が、ということですか?
秦
いや、ですから回想記で、一代記です。元慰安婦のね。
で、彼女は色んなところを転々としたんですけれども、最後ビルマに行ってるんわけ。
で、ラングーンにいたんです、これ首都のね。
利口で陽気で面倒見の良い慰安婦として、将軍から兵隊までね、人気を集め、チップが降るように集まったと。
萩上
はい。
秦
それで、5万円貯金が出来たと、2年余りでね。
そのうち5000円を軍用郵便で、下関郵便局へ送ったわけです。
萩上
それは何年頃の話ですか?
秦
昭和18年。戦争中ですね。
ですからね。これなんかもね、非常に楽しかったと、いうのが基調なんですよ。
だからね、中には悲惨な人もいたかもしれない。
しかしね、兵隊たちに良いサービスをしてもらうために、軍もそれなりに気を使うわけです。
それで、業者との間では大体、慰安婦側に立って有利になるようにしてやっている。
だからね、さっきの米軍の尋問調書でね、あれでもやっぱり性奴隷だと仰るんですか?
吉見
そうですね。
秦
ほう。だって四つの自由のうち、三つの自由は完全にあったわけですよ?
吉見
いやいや・・・
秦
居住の自由っていうのはね、これはね、看護婦さんもないですよ、居住の自由は。
だってね、まさか戦地でね、バスで通勤なんていうね、アパートも借りてなんて、そんなことはあり得ないでしょう。
吉見
それはあの看護婦さんと、それから慰安婦の女性達がさせられている事柄は全く違うじゃないですか。
看護をするというのはですね、本人にとってはそれは名誉なことですけれども、軍人たちの性の相手を毎日させられるということと、全く性格が違うんじゃないですか。
秦
それを論じたってしょうがないでしょう。
職業のひとつとして割り切ってるんだから。その代わりね・・・
吉見
いや、職業だと仰いますけれども・・・
秦
嫌な仕事かもしれないけどね。
吉見
誘拐で連れていかれた・・・
秦
軍司令官よりも高い給料もらってんだからね、みんななりたがるんですよ。
吉見
いや、それは幻想なわけでしょ。
…… to be continues.
(サルメラ こういう議論が不毛だと思う。
スーパーインフレで貨幣価値が下がって可哀相なのは慰安婦だけじゃないだろう。
劣悪な慰安所もあったろうし、そうでないところもあったろう。
いい思いした慰安婦もいたろうし、そうでなかったのもいるだろう。
騙したのは日本人もいたろうし、韓国人もいたろう。
そんなのは色々だ。
何でゼロか、100の議論になるんだ。
慰安婦制度は性奴隷制度だ。
それが当時、許されてた〝暗黙の了解〟制度だった。
ここまでは誰も異論はないだろう。
ここで議論してほしい核心は日本軍が率先して『強制連行』したか、どうか。
そして、それがあると言うなら、その証明責任は吉見教授にある。
ないことを証明するのでは悪魔の証明になってしまうのだから。
で、この部分、ここまで吉見はボカして議論し続けてるようにワタシには見える。
そして、
いよいよ、その核心に入る)
荻上チキ・セッション22 TBSラジオ
2013年6月13日
(大阪市庁舎内 記者会見)
橋下市長
軍自体、日本政府自体が暴行脅迫をして拉致をしたという、女性を拉致をしたという、そういう事実は今のところ証拠として裏付けられていないので、
そこはしっかり言っていかないといけないと思いますよ。
当時、慰安婦制度は各国の軍は持ってたんです。
当時はそういうもんだったんです。
ところが、なぜ欧米の方でね、日本のいわゆる従軍慰安婦問題だけ取り上げられたかと言ったら、
強制的に意に反して、慰安婦を拉致してですね、そういう職業に就かせたと。
レイプ国家だっていうことで、世界は非難してるんだっていうところをね、もっと日本人はね、
世界からどういう目で見られているかっていうところをもっと認識しなきゃいけないです。
------
荻上チキ
最初の論点ですが、橋下市長の発言がありましたが、その件で質問メールが来ています。
『橋下市長の一連の発言について、政治学的、歴史学的な面からどう評価されているか、お聞きしたいです』
秦郁彦
そうですね、まず、その政治的ということはね、歴史観側からはあれこれ言うべきことではないと思いますが、
まぁとにかく舌足らずであったと、そういう部分があちこちに見られたと、その辺が大きくクローズアップされたと思うんですね。
で、これは全然予定してなかったのがちょっと逸れて、この問題に入ったということで、まぁそういうことも考えてあげなきゃいかんだろうと思うんですけども。
事実関係に対してはですね、私は大体その通りだったと、ほぼ正確だったというふうに感じています。
荻上
例えば舌足らずだったというところはどういうところですかね。
秦
例えばですね、新聞報道なんかでは、当時のというのが、最初は抜けてたんですね。
ですから、まさに現在の時点でですね、慰安所は必要であったと、いうふうに彼が考えていると、とられたようですね。
後で言い直しましたよね。
だからこれはですね、聞いてる方もね、彼はずーっと戦後も後の生まれですし、
当時の日本軍の指導者たちが、慰安婦を、慰安所は必要であったと、考えて設立したと。
つまりそういう意味なんですね、本当は。
で、それが意図としてはちょっと舌足らずになっちゃったということでね。
他にもそういうのが何か所かあったと思います。
荻上
そのあとメディアに対して誤報だといったり、論争になったりしたということですけども、
橋下市長の会見について吉見さんはいかが思われたでしょうか。
吉見義明
うーん、まぁ、ちょっとビックリするような、とんでもない発言だったというふうに思いましたね。
というのはですね、舌足らずだったと仰いましたけれども、
慰安婦制度が必要なのは誰だってわかるわけです、というふうに仰っているわけで、これ素直に読めばですね、当時も現在も必要だったという発言になるわけですね。
それとセットになって、事実上、沖縄の米軍に風俗業の活用を勧めると、事実上買春を勧めるという考え方がピタリと平仄が合うわけですよ。
失言だとか舌足らずだとかじゃなくて、本音でそういうふうに言って、未だに撤回していないという点が非常に大きな問題だと思いますね。
荻上
今は許されませんよ、といった発言もそのあとにあったと思いますが、
それは別ということですか。
吉見
在沖米軍に風俗業の活用を勧めるということは撤回されましたけれども、
当時は彼はそれでいいんだというふうに思ってたんでしょうね。
ただし、前の方の発言はマスメディアの誤解だというふうに逃げてるわけですね。
未だに撤回はしてないわけですが、それは非常に不誠実な態度だと思いますね。
(サルメラ 誤解ではない。誤報、あるいは意図的な曲解、慰安婦問題を口にする政治家を問答無用にエジキにしてきたマスコミのいつものやり口だ。
ただ、橋下は他の根性なしの政治家と違い、最後まで謝らなかった、退かなかった、ということだ)
荻上
先ほど秦さんの方が、歴史的な事実に対しては大筋では正しいと言われてましたが、吉見さんは彼の思想とは別に、歴史の認識という面ではどうお考えですか。
吉見
歴史的な事実としても彼はよく知らないということではないかと思いますね。
荻上
どういう点で感じましたか。
吉見
一つは慰安所で女性たちに対する強制があったということ自体を否定しているわけですね。
それから慰安婦制度が性奴隷制度であるということも否定している。
しかし実際に、女性たちは慰安所に閉じ込められてですね、数多くの軍人の性の相手をさせられた。
で、それが非常にひどい状態であるというわけですね。
しかも、慰安所の制度というのは軍がつくった制度ですけれども、例えば居住の自由、もないわけですよ。
それから外出の自由もない。
廃業の自由もない、拒否する自由もない、というような状況のなかで、軍人の性の相手をさせられているわけですので。
そういう事実を彼は見落としてないということでしょう。
荻上
事実をめぐるご意見はお二人それぞれあるので、リスナーの質問を受ける形で、様々議論していただきたいと思います。
南部
次の質問です。
『慰安婦という言葉はいつできて、誰が作った言葉なのか、
そして世界的には慰安婦と同じような意味の言葉はあるのでしょうか。
教えてください』
秦
はっきりしないんですよ。
つまりね、慰安婦というのは少なくとも日中戦争期の軍の公文書のなかにも出てくるんですよね、慰安婦という言葉は。
それに従軍という言葉をつけたのは戦後、千田夏光 氏だといわれてるんですけど。
これもね確実とは言えませんね。
で、慰安婦とですね、どういう存在なのかというと、当時、日本は公娼制、つまり売春をですね、政府が認めてたわけです。
現在でも認めている国がありますけどね。
で、その業に従事している女性たちですね、これを娼妓と呼んでいたわけです。
ですから戦地における娼妓が慰安婦だと、実態はそういうことで、基本的には同じ公娼制のですね、延長線上であったと、考えていいと思います。
荻上
延長線上ということは全く同じものではないということですかね。
秦
まぁ、それはあの、当然のことながら一応戦地ですからね。
だから一番大きな違いはですね、内地の売春婦は、警察が監督してたわけですね。
で、戦地に行った場合には、慰安所の慰安婦たちは憲兵と軍医が監督してたわけです。
その違いですけどね。
憲兵はセキュリティ、つまり秘密漏洩とか、そういうことを防ぐためにですね、やはり関与してたということで、それ以外は大体、形態としてはそのまま延長線上、ということでね、
同じ女性が内地の遊郭で働いていて、今度はその高い給与をね、取れそうだということと、動員が大規模になりますとですね、内地から男はどんどん減っていくんですよ。
戦地に移っちゃうわけですね。
ですから、そこへ移動して同じことをやると、そういう意味です。
荻上
元々、公娼だった方も参加され、その延長線上だったということ、制度としては違う部分はあるけれども、意味合いとしては同じということになるわけですかね。
秦
制度上の違いじゃないですかね。
私に言わせればほぼ同じと考えていい。
荻上
ほぼ同じ。
秦
ええ。
荻上
吉見さんいかがでしょうか。
吉見
両者に関連があるということは言えると思いますけれども、明らかに別のものだと思うんですね。
荻上
公娼と慰安婦制度というものは。
吉見
ええ。
何故かっていうと、内地にある公娼というのは民間の業者が全部運営してるわけです。
軍の慰安所というのはそうではなくて、軍がつくりですね、軍が例えば建物を接収して、業者に使わせる場合もありますけれども、女性を集めるのも、軍が直接やる場合、それから軍が選定した業者に集めさせる場合もありますけれど、軍がやってるわけですよね。
それから慰安所の、規則も料金も軍が決めてるわけですよね、それから実際にそこを利用するのは、軍人、軍属に限られてるわけで、民間人はそこを使えないわけですから、明らかに違う、ということだと思うんですね。
それからもう一つは、内地の公娼制度も、僕は性奴隷制度だと思いますけれども、それはなぜかっていうと、要するに人身売買を基礎にして成り立っているわけですよね。
確かに、人身売買は公認されていて犯罪ではなかったわけですけれども、
慰安婦制度の場合はですね、その公娼制度よりももっと、なんていうんですかね、性奴隷制度の性格が強い。
それは例えば、内地の公娼制度の下ではですね、自由廃業という規定があったわけですね。
これ自由廃業っていうのは娼妓をやめようと思えば、すぐに辞められる権利なんです。
ただこれは実際は、紙の上の権利でしかないわけですけれども、まぁ、一応そういうものがあったわけですが。
荻上
公娼で携わっていた女性の告発とか日記とか見ても、やめさせられないという文章も当時もありましたですし。
吉見
そうですね。
荻上
今もね、風俗などもやめさせてくれない店などあったりしますけれどもね。
吉見
まぁ、建前としては辞められる、自由廃業の規定があったわけですけども、軍の慰安所では自由廃業の規定すらないわけですよ。
それは明らかに違うと思うんです。
荻上
なるほど。
元々の公娼制度も今から考えたら性奴隷的だと取れるし、ましてや軍の関わった慰安所に関しては、公娼よりもさらに進んで酷いという評価は妥当だろうということですかね。
吉見
それからもう一つはですね、国内で人身売買は犯罪ではなかったわけです、当時の刑法で。
国外に連れて行く場合は、国外移送目的人身売買罪というのがきちんとあるわけですよね。
女性たちが人身売買で、海外に連れてかれてですね、慰安所に入れられたとすれば、これは犯罪なわけですよ。
荻上
これは日本政府が犯罪だとしていたと。
吉見
そうですね。
当時の刑法でそれは3年以上の懲役、という非常に重い刑罰を科すことになっていたわけです。
で、仮に、人身売買をされて、慰安所に入れられたとすればですね、慰安所っていうのは軍の施設ですから、
そうすると、そこで女性たちを、いわば使役し続けるわけですから、軍の責任が生じてくる。
犯罪に加担してると言われてもしょうがないということになるわけですね。
それは明らかに違うと思いますね。
荻上
秦さん吉見さんの今の意見どうですかね。
秦
ちょっと私それはね、同意しかねますね。
内地の公娼制をね、これ奴隷だということになってくると、
そうすると、今現在オランダの飾り窓のね、女性たち、ドイツも公認してますしね、それからアメリカでもね、連邦はだめだけれども、ネバダ州は公認してるんですよ。
これみな奴隷、性奴隷てことになりますよね。
吉見
それは人身売買によって女性たちがそこに入れられてるわけですか?
秦
人身売買がなければ、奴隷じゃないわけですか。
志願した人もいるわけでしょ?
高い給料に惹かれてねぇ。
吉見
それは、まぁセックスワークをどういうふうに認めるかということについてはいろいろ議論があってですね。
それはむつかしいわけですけれども、少なくとも、人身売買を基にしてこういうシステムが成り立ってる場合は、
それは性奴隷制というほかないんじゃないですか。
秦
自由志願制の場合どうなるんですか?
吉見
それは性奴隷制とは必ずしも言えないんじゃないでしょうか。
秦
言えない?公娼であっても。
吉見
まぁ、それは本人が自由意思でですね、仮にそういうことを性労働をしているのであれば、それは強制とは言えないし、性奴隷制とも言えないでしょうね。
秦
だからね、日本の身売りっていうのはありましたね。
身売りっていうのはこれは人身売買だから、これいかん、てことになってるんですよ。
日本の法律でね。ですから・・・
吉見
いつ、いかん、てことになってるんですか?
秦
人身売買自体をほら、マリールイズ号事件の時からあるでしょう。ね?
だから、人・・・
吉見
それはだけど、たしかにあるけれども、それは建前なわけですよね。
秦
建前にしろですよ。
それでね、建前にしろですね、人身売買っていうのは、だいたい親が娘を売るわけですけれどもね。
売ったという形にしないわけですよ。
要するに金を借り入れたと。
で、それを返済するまでね、娘が・・・これを年季奉公と言ったりなんかするんですけどね、その間、その性サービスをやらされるってことなんでね。
それでね、娘には必ずしも実情が伝えられてないわけですね。
だからね、しかし、いわゆる身売りなんですね。
あれ昭和・・・
荻上
行ってみたら、こんなはずじゃなかった、というような手記が残っていた場合もあるわけですよね。
秦
騙しと思う場合もあるでしょう。
だから1936年のね、調査っていうのはあるんですが、
こういう売春婦達のですね、調査をやったところ、なぜなったかということについてですね、
家庭の事情というのがね、96%なんですよ。
つまり、娘達は親が自分を売ったということは思いたくないし、
で、そうであってもですね、これは言うに忍びない。
これは朝鮮の場合も同じだと思います。
だからそうするとね、娘たちは、騙されたと感じるのもあるでしょう、親も言いそびれますよね。
だからね、これはね、自由意思か、自由意思でないか、っていうのは非常に難しいんですね。
やはり家族のためにということですと、これ誰が判定するんですか?
吉見
いや、そこに明らかに金を払ってですね、女性の人身を、拘束してるわけですから。
それはもう人身売買というほかないんじゃないですか?
荻上
ちょっと時期は違いますけれども
吉原花魁日記とか、春駒日記とかの大正期の資料なんかには、
親に働いて来いと言われたけど、実際に来てみたら、このことだとは知らなかったと。
このようなケースもあったりするわけですよね。
それは親もあえて騙していたかもしれないし、
周りの人もお金が稼げていいね、と誉のように言うんだけれど、内実の話は周りも知らなかったっていう話は、いろいろあったりしますよね。
吉見
まぁ、実際にはあれでしょ。
売春によって借金を返すっていう、そういうシステムになってるわけでしょ。
秦
今だってそれはあるわけですよ。
吉見
それは、それこそまさに人身売買であって、それが問題になるんじゃないですか?
秦
じゃ、あなた、ネバダ州に行って、あなた、大きな声でそれを弾劾するだけの勇気がありますか?
吉見
いやいや、もし、それがですね、人身売買であればそれはやっぱり弾劾される・・・
秦
いやだから志願してる場合ですよ、自発的に。
自発か、売買か、
どこで区別するんですか。
吉見
いやいや、何を言ってるんですかあなたは!
売春で借金を返済するという、契約の下で・・・
秦
契約じゃないんですよそれは。
回歴後、返済するってことですからね。
大審院はね、逃げても構わないと。
しかし、最後は残ると、いうことですから。
結局やめられないんですよ。親が・・・
吉見
いや、それは、それは当時のですね、判決自体に問題があるわけですよ。
秦
大審院の判決?
吉見
そうです。
秦
だけど、みんな継がなきゃいかんですよ。
当時の人間は・・・
吉見
うん、あの結局ですね、一つの契約を二つに分けてね、売春で借金を返すのは違法だけれども、
借りた借金は返さないといけないっていう、判決がでるから、結局、女性たちは、遊郭から逃れられなかったわけですよ。
荻上
ここでいったん整理させていただきます。
公娼制度の中で、人身売買などの、性奴隷というふうに いわれるケースもあっただろうし、同意のものもあっただろう、
それは個々人によって見てはわからないけれど、
全否定することもできないだろうけれども、
全員がそうだったとも言えないわけですよね。
その実態というのはわからないと。
けれども慰安婦というもののなかで、公娼制度と同じような評価をするのであれば、そうしたものと同程度のものも、それこそ本人の意図に合わないものもあったんじゃないか。
吉見さんの言いたいことっていうのはそういったことなんでしょうかね?
吉見
僕は、日本軍慰安婦制度はですね、一つは人身売買を基礎にして成り立っている。
それからもう一つは、朝鮮から連れてかれた女性たちの中に非常に多いわけですけれども、
騙して連れてかれるケースが多いわけですね。
騙して連れて行くっていうのは当時の刑法でいうと、誘拐罪に該当するわけですよね。
だからその誘拐罪を基礎にして成り立っている。
それからある場合は、法律上でいうと略取と言いますけれども、
暴行脅迫を用いて、連れて行くケースも、あるわけですよね。
それからもう一つ、付け加えて言いますと、例えば占領地なんかでは、軍がですね、地元の有力者に女性を出せというふうに、要求をしますよね。
でこれは、現地の軍がオールマイティなので断れないと。
そうすると誰か犠牲者を差し出せということになるんですが、これは権力濫用による半強制。
中国なんかではこういう例が非常に多かったと思うんですが、
そういうものを基礎にして成り立っているシステムだと思うんですね。
荻上
今の話は意に反して、慰安婦になる人がいたとした場合、その意に反してさせたのはだれか、とつながってくると思うんですけど、秦さんの考えだとどうですかね?
秦
それはねぇ、朝鮮人たちの身の上話であるんですよ。
これがね身の上話AとかBとかね、
酷いのになると一式5通りぐらいあるんですよ。
荻上
証言がですか?
秦
そうそうそう、
それでね、どれが本当かわからないけどね、だからある段階から、朝鮮人の慰安婦のね、慰安婦になった同期としてはですね、主語を全部外しちゃったんですよ。
つまりね、騙されてとか、連行されてと、いうのをね、これ取っちゃったんですね。
荻上
証言の中から?
秦
証言の上からね、で、これはあの、向こうの支援団体の挺対協というのがね、当然、協議してやってると思うんですよ。
荻上
向こうというのは韓国のことですよね。
秦
ええ韓国ですね、ですから、なぜ主語が無いかと言うと、これは私に言わせてもらえば、これ皆、朝鮮人なんですよ。
朝鮮人の親が、朝鮮人のブローカーに売って、そのブローカーが、朝鮮人の抱え主にまた売ると、ね?
いうことで、ここまではほぼ一本ですよ。
この中でね、だから、その中の内情というのはわかりません。
だから一切、それは韓国側からは出てこないわけです。
だから私は初期のころね、ブローカーを見つければね、全貌がすぐわかるよっていうんですけどね、日本はね、そんなことはね、到底、韓国政府には頼めないっちゅうんですよ。
だから一切ブローカーが出てきたことない。
それから親が売ったという話も出てこないわけですね。
だけど大体、私は大多数は今のルートで、それでその抱え主ね、になると、これ日本人もいます。
で、それが戦地に行って、軍と渡りをつけるわけです。
そうすっと、これ需要と供給ですからね、一種の商談なんですよ。
だからどっちが頼んでとか、どっちが主導してとかいう、そういう問題じゃないんですね。
荻上
そうすると、そういう市場があって、それに商品を提供していた側というのはそれこそ韓国の側、ブローカーの側とか、家族の側から提供していたのであって、
そこに騙されたというのがあったとしても、そこに軍の責任などを問われるような類のものではないんじゃないかと、いうことですかね。
秦
それはなぜかって言いますとね、
このブローカーまでの段階というのは、契約というのがあるわけですよね。
それから抱え主との間までも、契約書はある。
それから軍と抱え主との間でね。
連れてきた慰安婦も、それから抱え主も、軍のメンバーじゃないんですよ。
嘱託でもなければ・・・
だから、御用商人なんですよ。
御用商人が女性たちを連れてきていかがですか、と・・・っていうことで商談、一種の商談が行われると。
で、その結果、両方の、需要と供給が合致してですね、それでそこに慰安所ができると。
ま、こういうことですよね。
簡単に言えば。
荻上
一つだけ確認なんですけど、その御用商人というのは、誰でもなれたというわけではないんですか。
ある種の許可制と言いますか、軍の許可証を持ってないと、というのもあるわけですか。
秦
いやいやいや、そうじゃないです。
それはいろいろなコネやなんかでね、ルートをつけて、御用商人って、みんなそうでしょ?
この人は宮中御用達、なんて看板出してるのもありますけれどもね。
あれは一体、本当に認めてるのかどうかわかりませんよね?
納入したこと一回でもあると、そういうふうに言ってるのかもしれません。
だから、私は御用商人だと、考えればいいわけで、
だから民法上の関係はそこで切れちゃうわけです。
だから、軍の方では女性たちがね、どうやって連れてこられたかということはわからない。
荻上
その段階で軍の責任は切れている、という話だと思いますけれど、
吉見さんは今の責任論についてはどうですかね?
吉見
ええとですね、
まず、業者ですけれども、これは軍が選定した業者ですね。
あるいは、軍が頼まれて総督府が選定した業者が集めているわけですよね。
身分は、軍属の待遇を与えられている、と思います。
秦
違います。
吉見
いや違わないですよ。
秦
軍属名簿というのはありますよ、ちゃんと。
それにありません。
だから、軍属待遇っていわれるでしょ?
吉見
ええ。
秦
いかにも軍属と同じだと、ね。
しかし軍属だと給料が払われるはずですよ。
吉見
いや、あの国会のですね、厚生省の答弁なんかでは無給軍属だと、いうような言い方をしてますね。
荻上
無給軍属というのは給料を払われない?
吉見
給料は払われないけれども、純粋の民間人だと軍用船に乗せるわけにもいかないし、軍の施設を使わせるわけにもいかないので、そういう身分を与えているということですね、そういう言い方をすると・・・
秦
女にも与えたということですか?
吉見
そうですね。
秦
女にも軍属の?
吉見
無給軍属。
秦
そんなのはありえませんよ。
吉見
というふうに、厚生省の答弁はしてますよ、ちゃんと・・・
秦
それは一般論の話でしょ?
吉見
一般論じゃなくて、国会答弁でちゃんとそういうふうに・・・
秦
ちゃんと慰安婦もと、言ってるんですか?
吉見
言ってますよ、ちゃんと。
秦
それはありえないですね。
吉見
いや、あの・・・
荻上
それはいつごろの答弁ですか?
吉見
ええっと、ですね。
ちょっと待ってください。
荻上
当時のっていうことですか。
吉見
いや戦後ですね、戦後・・・
秦
南方へ行く場合はね、あらゆる人がね、全部、船に乗っていかにゃいかんわけですよね。
それで船は全部、陸軍がコントロールしてるわけです、配船はね。
だから便宜供与なんですよ、それに乗るいろんな人はね。
吉見
だから民間人は乗れないわけですよね。
秦
いや、乗れますよ、便宜供与で。
吉見
いや、それはだから軍属待遇・・・
秦
たくさん進出してるんですよ、向こうにね。
吉見
軍属待遇にして、いるわけでしょ?
秦
正式な軍属待遇じゃないんですよ。
荻上
特別にこの人たちは船に乗っていいというような形で・・・
秦
ええ。許可するわけですよ。
荻上
その場その場で許可出してるというわけですね。そうなると・・・
吉見
昭和43年の社会労働委員会の会議録、昭和43年4月26日ですね。
『一応、戦地によって、施設宿舎等の便宜を与えるためには何か身分がなればなりませんので、無給の軍属というふうな身分を与えて、宿舎等、便宜を供与していた。
こういう実態でございます。』
という答弁がありますね。
秦
誰ですか、答弁したのは。
吉見
これはですね、サネモト政府委員。
厚生省のお役人だと思うんですが・・・
秦
厚生省がね、それは認識が間違ってますよ。
吉見
いや、実態に合ってるんじゃないですかね。
秦
それはね、軍属待遇にするというね、事例なんか出てないはずですよ。
だからそれはね、乗船許可を出すということはね、「と見なす」というね、
そういうことであってですね、
なんら身分関係はないんですよ。
吉見
それからですね、外務省の公文書によりますと、慰安婦や慰安業者については軍従属者という身分を与えているわけですね。
この軍従属者っていうのは、純粋な民間人ではないということでしょうね。
それからもう一つはですね、その軍によって選定された業者は、例えば人身売買とか、誘拐という犯罪を犯して、女性を海外に連れて行ってですね、軍の慰安所に入れるわけですよね。
で、そのときに、軍の慰安所は女性たちをチェックしないかっていうとチェックしてるわけですよ、くわしく。
秦
どうやってチェックするんですか。
吉見
それは契約関係を調べたりですね、いろんな書類を見てチェックしてるということは・・・
秦
いやー、そいじゃわからんでしょ。
そんなことを書く人はいませんよ。
吉見
いや、それはね・・・
秦
女たちもね、自分はね、無理やりね、連れてこられたなんて言いませんよ。
そしたらね、結局ね、仕事を失うんですよ。
いくらでも補給源はあるわけですからね。
そんなことは言いませんよ。
吉見
いや、そういう例があるんですよ。
言っている・・・
秦
それはインフォーマルにでしょ。
吉見
いやいや、一つの例を示しますとですね、あの有名な、「漢口慰安所」という元軍医さんが書いたあの本の中にですね・・・
秦
あぁ、あの本ですね。
吉見
日本から連れてこられた若い女性がですね、前歴もないと書かれているので、売春の経験のない女性ですね。
その女性が、性病検査の時にですね、
こういう風に言ってるわけですね、私は慰安所というところで、兵隊さんを慰めてあげると聞いてきたのに、こんなところでこんなことをさせられるとは知らなかった。
帰りたい、帰らせてくれ、というふうに泣いて、性病検査を拒んでいる。
その日はできなかった。
翌日、泣き腫らしてですね、体ブルブル震わせながら性病検査に応じるんですが、たぶん業者に殴られてそうされたんだろうというふうに長沢健一さんという軍医さんは言っているわけです。
つまり、慰安所の・・・
荻上
軍の関係者の側が言っているわけですか?
吉見
そうです。
この女性は慰安所で働くということは聞いてるんだけれども、その慰安所というのは何か、軍人の性の相手をさせられるっていうことを知らないできたわけですね。
ですから、これは騙して連れてこられてるわけですから、誘拐罪に該当するはずですね。
秦
だってそれをどうやって立証するんですか。騙したということを。
吉見
いや、この女性がそういうふうに言って・・・
秦
信じるわけですか、その人のいうことを。
吉見
勿論そうですよ。
秦
だってどの程度のね、インテリジェンスのある人かわからないですがね、
慰安所行くといってですね、しかも戦地のですよ、誰かに聞きゃあいいじゃないですか、その辺の大人に。
ね?そうすりゃね・・・
吉見
そりゃあれですよ、秦さんみたいに教養のある人はそうだけれどもですね・・・
秦
だって、そりゃレベルの高い人でしょ?わりと。それ違うんですか。
吉見
いや違いますよ、田舎から連れてこられた女性だというふうに・・・
秦
それを言い出したらね・・・
吉見
いや違いますよ、田舎から連れてこられた女性だというふうに・・・
秦
それを言い出したらね・・・
吉見
それからもう一つ言いますとですね、この女性は重い借金を負っている、というふうに長沢軍医は言っているわけです。
秦
だからそれもおかしいですよね?
吉見
それでつまり、誘拐罪でもありですね、人身売買罪にもなるわけですよ。
ところが、結局この女性は解放されないでそのまま軍の慰安所に入れられてしまうわけですね。
これが犯罪だっていう認識が軍の側にないっていうのは、非常におかしいですよね。
荻上
認識としてということですかね。
吉見
こういう事態が起こったらですね、女性は解放して送り返さなきゃいけないはずですよね。
秦
じゃあその前に業者の方の責任もありますわね。
吉見
業者は逮捕しなきゃいけないということになるわけですね。
そりゃもちろん、送り出した警察もちゃんとチェックしてないという問題もありますよね。
荻上
前提としてそうしたふうに嫌だ嫌だと言った場合は、帰るっていう自由はあったんですか?
秦
借金を返せばね、借金を返せば何の問題もないわけですよ。
吉見
つまり、借金を返すまでに何年間かそこに拘束されるわけですよね。
秦
そうすると親が最後は返さにゃいかんのですよ、親が。
吉見
それが性奴隷制度だっていうことですよ。
秦
親が売ったのが悪いでしょ。
吉見
いやいや、秦さんがわかってないのはそこですよ。
秦
どうして。
吉見
借金を返せば解放される、っていうんであれば、それはあれですよね、人身売買をそのまま認めてることになるじゃないですか。
荻上
ちょっとここで一通、質問メールが来ています。
南部
『従軍慰安婦だった女性たちは戦争が終わった後、無事故郷に帰れたんでしょうか?
多くの人が亡くなったという本を読みましたが、事実はどうだったかを教えてください』
荻上
その本のタイトルも気になりますが、これは秦さん、どうでしょう。
秦
えー、私は自分の本の中でね、それを計算したんです。
生還率は控えめにみて、9割以上と。
荻上
9割以上。
秦
ええ、実際はね、日赤の看護婦さんなんかがね、96%以上なんですよ、生還がね。
大体ね、慰安婦とそれから看護士さんによる野戦病院はね、前線から離れた、比較的安全な場所にいたわけですね。
しかし戦争末期になりますとね、そうもいかなくて、戦闘に巻き込まれたこともあるし逃げ遅れてね、それから玉砕地っていうのがあるでしょ?島でね。
だからそういうのも考慮にしましてね、私は日赤の看護婦さんの、生還率より低かったことはないだろうと。
荻上
そうなると大体9割以上はあるだろうと。
秦
ええ、そうです。
荻上
吉見さん、どれぐらいの方が還られたんでしょうね。
吉見
何%というのを計算したことはないんでわからないんですけれども、たぶん日赤の看護婦さんよりももっと生還率は悪かったんじゃないかと思いますね。
というのは、慰安所の生活というのは非常に厳しくてですね、毎日数人から数十人の男性、軍人の相手をさせられるということが続くわけですよね。
その中で性病を移されたり、体を悪くしたり、そこで病気で亡くなるっていうケースも非常に多いと思いますので、戦地で命を落とした、女性は決して少なくなかったんではないかということは言えると思うんですね。
荻上
まぁ、これももちろん推計ということで、実際にそういった名簿がもちろんあるわけではないので、カウントすることは難しいと思うんですが。
この後も橋下市長の会見などでもしばしば話題になる、強制連行ということもありますし、また軍の関与とか、その後の論争以降の責任の取り方論などの議論のポイントを、続けていきたいと思います。
(サルメラ やや、質問の意図とその回答がズレてるというのが個人的印象。
とくに、吉見教授から聞きたかったのは、
人身売買云々の、誰の責任、誰の罪なのかが まぎらわしい話でなく、もっと直接的な、
『道端歩く女性を突然脅しつけトラックに乗せるという誘拐の例は頻繁にあったのか』
『過労とか病死とかでなく、いわゆる拷問などによるリンチ殺人が特殊でなく、何例もあがっているのか』
というところ、
吉見教授もこうした物語を信じているのか、ということだ)
荻上
強制連行や河野談話の評価についての話をしようと思っているんですが、秦さんから先ほどの議論の補足があるということで、いかがでしょうか。
秦
最近あの、吉見さんがですね、しばしば繰り返して仰ってることなんですけれども、強制連行があったかどうかっていうのは、大した話じゃないと、今はね。
現在は4つの自由がなかった、慰安所における性奴隷というね、こちらの方がずっと重要なんだと、いうことを何度も言っておられるんで。
で、私は強制連行はなかったと思いますけれども、また議論するとね、橋下さんのような議論になっちゃいますんでね。
今の慰安所の状況がそんなに酷いものであったのかどうかと、いうことをちょっと申し上げたいと思うんですけれども・・・
荻上
劣悪な環境で働かされた、だから性奴隷だっていうけれど、そもそも劣悪だったのか疑問があると。
秦
そういうことです。
4つの自由というのはね、これは吉見さんが居住の自由、外出の自由、廃業の自由、接客拒否の自由、がないというね。それをない、
それは慰安所の女性が文字通りの性奴隷だ、というふうに述べておられるわけですよ。
それがところが、吉見さんが編纂された従軍慰安婦資料集というのがあるんですね。
これにですね、1944年、北ビルマに捕えられた韓国人の慰安婦20人に対する米軍の尋問書というのがね、入ってるわけですよ、訳されたものがね。
で、その中でどういう生活だったんだということを聞かれてですね、こういうくだりがあるんです。
『兵隊さんと一緒に、運動会、ピクニック、演芸会、夕食会などに出席して楽しく過ごした。
それから次にですね、お金はたっぷり貰っていたので、暮らし向きは良かった。』
荻上
それは慰安婦当事者の発言ですか?
秦
そうですね、20人の証言です。
それから蓄音機も持ち、都会では買い物に出かけることが許されたと、接客を断る権利も認められたと、それから一部の慰安婦は、朝鮮に帰ることを許されたと。
兵隊さんから結婚申し込みの例はたくさんありましたと、いうのがありましてね。
何よりも月の収入がですね、750円、彼女たちのね、その頃日本の兵隊さんはね、命を的に戦ってるんですけれど、月給は10円ぐらいなんですよ。
つまり、75倍という高収入を得ていたわけですね。
荻上
高収入でなおかつ楽しかったという発言があると。
秦
それもありますね、それから日赤の看護婦さんの10倍です、この金額は。
さらにですね、軍司令官や総理大臣より高いんです、この通りなら。
まぁ、大体似たり寄ったりだったと思うんで。
で、私はこういう状況下にある女性たちがね、性奴隷であったと思えませんね。
雇い主よりも遥かに高い収入を得ている奴隷なんてこの世の中にいます?
荻上
っていうのは、今の吉見さんへの質問ということですね。いかがでしょう。
吉見
ええとですね、まずこれは女性たちがこういうふうに言ったと 仰いましたけれども、
この尋問調書はですね、2名の業者と、それから20人の朝鮮人女性のヒアリングを、アレックス・ヨリチという人が聞いて、まとめてるわけ・・・どの部分が、被害者の女性の証言であり、どの部分が加害者側の証言かよくわからないという点があります。
それからもう一つはですね、将兵と一緒にスポーツ行事に参加したというふうなことがありますが、これは多分ですね、戦地で女性がいないので、慰安婦をそういうところに連れ出すとか、宴会に連れ出すと、いうようなことであったと思います。
夕食会に出席したということも、あると思うんですね。
もう一つは高収入だということですけれども、当時のですね、ビルマのものすごいインフレということをですね、考慮に入れておられないというのは非常におかしなことだと思いますね。
ビルマはですね、軍票を大量に増発して、1943年ごろからものすごいインフレになるわけですね、
荻上
インフレというのはお金の価値が下がるということですよね。
吉見
そうです、1945年になるともう軍票はもうほとんど無価値。
それで女性たちがなぜそれだけのお金を持っているかというと、慰安所に通う軍人がですね、持ってても何も買えないので、チップとして女性たちに渡すわけですよね。
南部
すいません、軍票ってなんでしょう?
吉見
軍隊が占領地で発行する、軍用手票っていう紙幣に代わるものですね。
で、この時期は南洋開発銀行というのがそういうものを出してたわけですよね。
荻上
後ほどお金に引き換えるっていう。
吉見
そうですね、まあ一応。
現地のまあ、例えば1ルピーは日本円で1円ということになっていたんですけれども、内地と比べてですね、ものすごいインフレになるので、外資金庫というのをつくって、そのインフレが内地に及ばないようにしていた訳ですね。
で、現地ではその軍票を持っていても、ほとんど何も買えないので。
荻上
名目上の金額だけだったと。
吉見
ええ、ほとんどそういう状態になってるわけ。
それからもうひとつはですね、秦さんが引用されなかったところがあるんですけれでも、えーと、女性達はですね、それだけのお金を持っているけれども、すぐに生活困難に陥ったと、いうふうなことが書いてあるんですね。
荻上
同じ証言ですか?
吉見
ええ、同じ証言です。
もしそれが高額であればですね、どうして生活困難に陥ることが起こるんでしょうかね?
これはインフレということを考えないとわからないんではないかと思います。
それからもう一つは、同じ引用されたこの「捕虜尋問報告」の一番初めでですね、女性達はどういう形でビルマに連れて来られたのかということを書いてる部分があるんですけれども、その部分を見ますとですね、
こういうふうに言っています。
1942年5月に日本の周旋業者達が朝鮮にやってきて、女性達を集めた訳ですけれども、その役務の、まあ仕事の性格は明示されなかったけれども、それは病院にいる負傷兵を見舞い、包帯を巻いてやり、そして一般的に言えば、将兵を喜ばせる事に関わる仕事であると考えられていた。
これはまあ誘拐ですよね、騙して連れてくるわけですから。
荻上
う~ん。
吉見
それから、これらの周旋業者の用いる誘いの言葉は、多額の金銭と家族の負債を返済する好機、それに楽な仕事と新天地における新生活という将来性である。
これは甘言にあたるので、これも誘拐罪を構成します。
で、このような偽りの説明を信じて多くの女性が海外勤務に応募し、200~300円の前渡し金を受け取った、というふうにありますので、人身売買でもあるわけです。
荻上
う~ん。
吉見
で、こうして、現地で慰安所の生活に拘束されたというふうに書いているんですよね。
荻上
じゃあ、ちょっと今の質問に変えますと、当時インフレだったということを考慮しないのか、というのが一点と、それから、その、今読みあげていただいた方々のそもそも来た理由というものが、甘言、騙されて来ている方々なので、それはどうなんだ、っていう話で・・・
秦
あれは騙したんですよ。
萩上
誰が騙したんでしょうか?
秦
まずほとんど朝鮮人でしょうね。
吉見
これ日本の周旋業者って書いてありますよ。
秦
え?
吉見
日本の周旋業者が朝鮮にやってきて・・・
秦
日本人のですか?
吉見
いやいや、日本のだから日本人でしょう。
秦
いや、当時、日本人なんですよ朝鮮人はね。いや、だいたいね・・・
吉見
それはですね・・・
秦
当時ね、朝鮮に住んでた日本人でね、朝鮮語でね、朝鮮人を騙せるほどね、朝鮮語の上手い人、ほとんどひとりもいなかったと思います。
だから、騙せませんよ。
吉見
元締めが、日本の業者で、手足としてですね、地元の業者を使うということはよくあることですよね。
それから、この周旋業者というのは軍に選定された人物であって、軍から色々、便宜を計ってもらって、まあ誘拐とか人身売買やってるわけですよね。
しかしこれは犯罪なわけでしょ。
それで、連れてった元はどこに入れるかっていうと、軍の施設である慰安所に入れるわけですよね。
そうするとそこで軍の責任は発生しないんですか?
どういうふうにお考えですか?
秦
そこは関係がないわけですよ。
朝鮮総督府の管内で、ですよ。
吉見
いやいや・・・
秦
朝鮮人が、騙したということね。
で、それをね、ちゃんとその旅行許可を出してるわけでしょ。
そうするとね、朝鮮人の巡査もいたわけですな。
それでどうしてそういう騙しを摘発しなかったんですか?
萩上
う~ん。
あのちょっと先ほどの話に戻ってですね、気になったのが、先ほど、そういった証言もあって楽しかったという話もあったということなんですけれども、それは他の慰安所でも同様に楽しかったということになるんでしょうか?
秦
例えばね、こういうのがあります。
文玉珠(ムン・オクチュ)というね、慰安婦なんですがね。
彼女の一代記が本になってるんですよ。
これがね、山川菊枝賞をもらったと・・・
荻上
当事者の発言が、ということですか?
秦
いや、ですから回想記で、一代記です。元慰安婦のね。
で、彼女は色んなところを転々としたんですけれども、最後ビルマに行ってるんわけ。
で、ラングーンにいたんです、これ首都のね。
利口で陽気で面倒見の良い慰安婦として、将軍から兵隊までね、人気を集め、チップが降るように集まったと。
萩上
はい。
秦
それで、5万円貯金が出来たと、2年余りでね。
そのうち5000円を軍用郵便で、下関郵便局へ送ったわけです。
萩上
それは何年頃の話ですか?
秦
昭和18年。戦争中ですね。
ですからね。これなんかもね、非常に楽しかったと、いうのが基調なんですよ。
だからね、中には悲惨な人もいたかもしれない。
しかしね、兵隊たちに良いサービスをしてもらうために、軍もそれなりに気を使うわけです。
それで、業者との間では大体、慰安婦側に立って有利になるようにしてやっている。
だからね、さっきの米軍の尋問調書でね、あれでもやっぱり性奴隷だと仰るんですか?
吉見
そうですね。
秦
ほう。だって四つの自由のうち、三つの自由は完全にあったわけですよ?
吉見
いやいや・・・
秦
居住の自由っていうのはね、これはね、看護婦さんもないですよ、居住の自由は。
だってね、まさか戦地でね、バスで通勤なんていうね、アパートも借りてなんて、そんなことはあり得ないでしょう。
吉見
それはあの看護婦さんと、それから慰安婦の女性達がさせられている事柄は全く違うじゃないですか。
看護をするというのはですね、本人にとってはそれは名誉なことですけれども、軍人たちの性の相手を毎日させられるということと、全く性格が違うんじゃないですか。
秦
それを論じたってしょうがないでしょう。
職業のひとつとして割り切ってるんだから。その代わりね・・・
吉見
いや、職業だと仰いますけれども・・・
秦
嫌な仕事かもしれないけどね。
吉見
誘拐で連れていかれた・・・
秦
軍司令官よりも高い給料もらってんだからね、みんななりたがるんですよ。
吉見
いや、それは幻想なわけでしょ。
…… to be continues.
(サルメラ こういう議論が不毛だと思う。
スーパーインフレで貨幣価値が下がって可哀相なのは慰安婦だけじゃないだろう。
劣悪な慰安所もあったろうし、そうでないところもあったろう。
いい思いした慰安婦もいたろうし、そうでなかったのもいるだろう。
騙したのは日本人もいたろうし、韓国人もいたろう。
そんなのは色々だ。
何でゼロか、100の議論になるんだ。
慰安婦制度は性奴隷制度だ。
それが当時、許されてた〝暗黙の了解〟制度だった。
ここまでは誰も異論はないだろう。
ここで議論してほしい核心は日本軍が率先して『強制連行』したか、どうか。
そして、それがあると言うなら、その証明責任は吉見教授にある。
ないことを証明するのでは悪魔の証明になってしまうのだから。
で、この部分、ここまで吉見はボカして議論し続けてるようにワタシには見える。
そして、
いよいよ、その核心に入る)